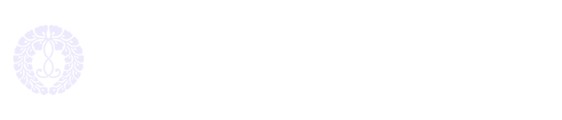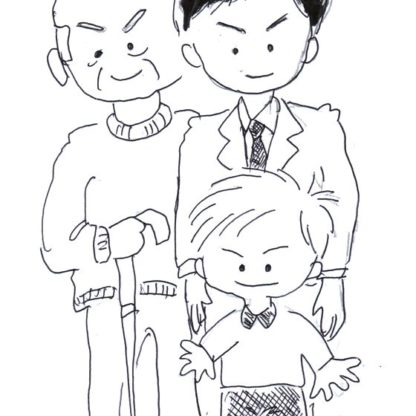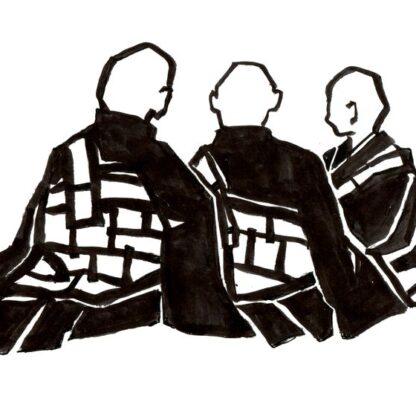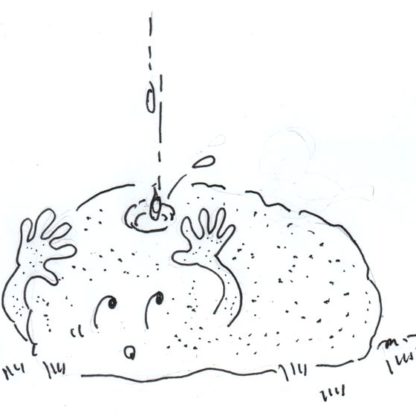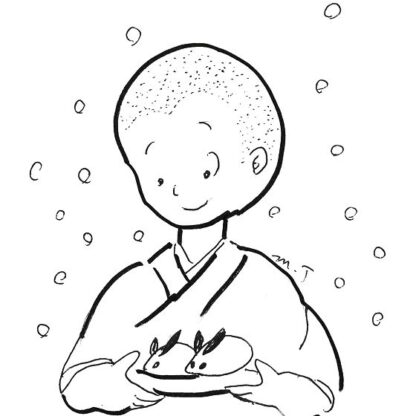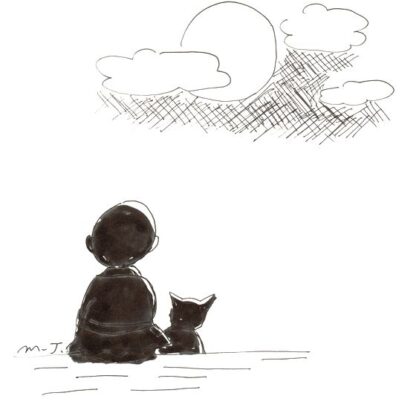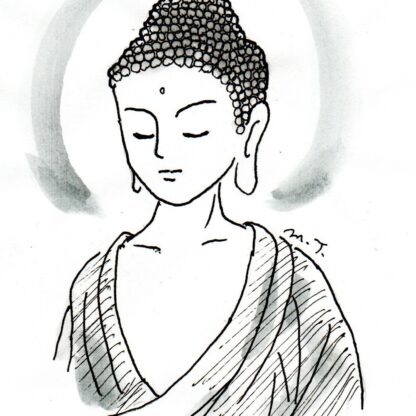蓮如上人の御生涯 13
「堅田大責(かただおおぜめ)」

 蓮如上人が身を寄せていた堅田は、琵琶湖の港町としてとても栄えていたよ。堅田は山が湖にせまる土地で農業は難しく、早くから湖の産業を行っていたんだけど、ある時船を使った運搬業をはじめたんだ。この運搬業が大当たり。その力は琵琶湖内にはおさまらず日本海に進出し、北は出羽(秋田)から西は石見(島根)までの運送をにない、莫大な利益を上げたよ。足元の琵琶湖の支配権をにぎり、通常の運送料だけでなく上乗という琵琶湖の通行税を取り、とても繁栄していたの。
蓮如上人が身を寄せていた堅田は、琵琶湖の港町としてとても栄えていたよ。堅田は山が湖にせまる土地で農業は難しく、早くから湖の産業を行っていたんだけど、ある時船を使った運搬業をはじめたんだ。この運搬業が大当たり。その力は琵琶湖内にはおさまらず日本海に進出し、北は出羽(秋田)から西は石見(島根)までの運送をにない、莫大な利益を上げたよ。足元の琵琶湖の支配権をにぎり、通常の運送料だけでなく上乗という琵琶湖の通行税を取り、とても繁栄していたの。
そんな中、事件が起きるんだ。応仁二(1468)年、室町幕府が将軍の「花の御所」再建のために調達した木材が琵琶湖をとおして運ばれたんだけど、上乗を払わないことを理由に堅田衆が積荷を差し押さえちゃったんだ。激怒した室町幕府八代将軍足利義政は、比叡山延暦寺に堅田を攻めるよう要求したんだ。
同年4月16日、比叡山は堅田に対して焼き討ちを行ったよ。堅田衆はもちろん全力で戦ったんだけど、町は四方から攻撃され、湖からの大風に煽られ火が回り、5日に渡る攻防のすえ堅田の町はほぼ全域が焼失、堅田衆は琵琶湖に浮かぶ沖島に逃れたよ。これが世にいう堅田大責(かただおおぜめ)だよ。
本福寺の法住は焼き討ちの情報をいちはやく察知し、蓮如上人と親鸞聖人の祖像を大津に移したよ。祖像と上人を船にのせ、比叡山衆徒が警戒している坂本沖を猛スピードで突破したんだ。「ここを先途と、水夫にまいらるる人、腹筋を切て押し申」と、『本福寺跡書』にはその必死なようすが記されているよ。
大津には道覚の道場があり、祖像はここに移され難をまぬがれたよ。でも、ちょっと手狭だったので、三井園城寺と交渉し、園城寺の境内南別所の近松に坊舎をたて、ここに祖像を移すことになったんだ。三井園城寺は寺門といい、山門の比叡山延暦寺とは平安時代から対立していたの。だからその境内に坊舎をたてることで、ようやく祖像を安全な場所に安置することができたんだ。